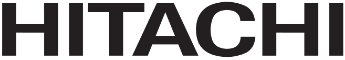115年間受け継がれる存在意義「社会への貢献」を未来に繋げ、 グループ28万人でハーモナイズドソサエティの実現に貢献する
執行役社長兼CEO
德永 俊昭

創業時から掲げる不変の理念が、 サステナブル経営の根幹
私は、CEOとして経営を行っていくうえで重要なことは、企業が何のために存在するのか、即ち「存在意義」を絶えず意識することだと考えています。歴史ある企業であっても、存在意義が揺らいだり顧みられなくなると、たやすく衰退したり、最悪の場合消滅してしまうことを、数多くの事例が証明しています。
日立グループにとっての存在意義は、創業者・小平浪平が掲げた「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」という企業理念です。日立は創業以来115年にわたり、時代の変化を先読みして提供する価値を変化させながら、「社会に貢献する」ことを不変の存在意義として、成長してきました。現在は、IT、OT(制御・運用技術)、プロダクトを活用してお客さまや社会の課題を解決する社会イノベーション事業をグローバルに展開しています。
未来にわたって日立がこの存在意義を果たし続けるために、私は日立をデジタルセントリック企業へと変革することにより、持続的な成長を実現する必要がある、と考えています。この強い意志のもと、2025年4月に発表したのが新たな経営計画「Inspire 2027」です。IT、OT、プロダクトを併せ持つという、世界でも類を見ない日立の強みを活かし、デジタル技術を活用して事業同士の連携を一層深化させることで、環境・幸福・経済成長が調和する「ハーモナイズドソサエティ」の実現に貢献することをめざしています。
トレードオフを克服し、社会課題解決を成長へ繋げる
日立は常に社会に貢献しながら成長し、企業価値を向上させてきた企業です。これまでの中期経営計画においても、財務目標を設定しつつ、地球環境の保全やウェルビーイングの追求を掲げてきましたが、ともするとトレードオフの関係になりかねないこれらの価値を同時に実現するためには、それぞれの価値を個別に捉えるのではなく、一つのものとして統合して考えなければなりません。
今回「Inspire2027」でビジョンとして掲げた「ハーモナイズドソサエティ」には、こうした経営チームの意志が込められています。日立がお客さまや社会の課題を解決し、持続可能な社会づくりに貢献することが、会社と従業員双方の成長を実現するとともに、ステークホルダーの皆さまへの還元に繋がる。私はこのような好循環を回すことで、日立が持続的に成長していく未来を実現したいと考えています。
日立にとってサステナビリティは事業活動の基盤であり、その実践には、さまざまな事業部門が共有でき、かつ一貫して取り組むことのできる、クリアな戦略が求められます。
そこで「Inspire 2027」では、グループ一丸でサステナビリティ経営をより強固に推進するため、新たな戦略「PLEDGES」を策定しました。「PLEDGES」は、日立のサステナビリティ戦略を支える7つの柱と、今後3年間でめざすべき目標を示したフレームワークです。この「PLEDGES」によって、サステナビリティと事業活動のさらなる統合を後押しし、「地球環境の維持、人々と社会への価値提供」と「日立の持続的成長」を同時に加速させます。
存在意義をグローバルに共有し、「ワン・カンパニー」として経営
CEOの大切な役割は、企業の存在意義を体現し、従業員をエンカレッジすることです。それが、企業の成長を実現し、ひいては社会の持続可能性を高めることに繋がるからです。
創業の地である茨城県日立市で生まれ、日立グループを身近に感じて育った私にとって、「社会への貢献」という存在意義は、自分自身の職業人としての原点でもあります。一方で、日立のグローバル事業の拡大に伴い、売上収益と従業員数の約6割を海外が占めるようになった今、この存在意義はグローバルに共感を得られるのだろうか、との懸念を抱いたこともありました。
しかし2021年、シリコンバレーのデジタル企業であるGlobalLogicを買収した際、彼らは「日立グループに入れば、社会的に意義のある仕事ができる」という思いで、仲間に加わることを選んでくれました。たとえ言語や文化が異なっても、日立の存在意義や価値観は世界に共有できるものだと確信するきっかけとなりました。
CEOに就任した4月以降、日立のDNAに刻み込まれた「社会への貢献」という信念を、世界各地の従業員と共有することに力を注いでいます。組織に最も大きな変化をもたらすことができるのは、「共感」のもと人が団結した時です。全世界の日立グループ従業員がその存在意義に共感し団結することができれば、必ずやこれまでにないイノベーションを起こし、成長に繋げることができると考えています。
私は、日立を「ワン・カンパニー」として経営することで、さらに進化し、企業価値を向上させることができると確信しています。オーガニック成長を実現した「2024中期経営計画」では、個々の事業の稼ぐ力は向上したものの、事業同士の連携の深化はこれからです。
幅広い事業同士が、デジタル技術を活用してより深く連携する「真のOne Hitachi」で、IT、OT、プロダクトを併せ持つ日立ならではの強みを新たな価値として創出すれば、社会が直面するより複雑な課題を解決できると考えています。就任以来、日立の存在意義と、「真のOne Hitachi」による成長を繰り返し説く中で、会議の場でリーダー同士が自らの担当範囲にとらわれずに闊達に議論したり、従業員から連携の深化への要望が聞こえてくるなど、意識や行動が着実に変化し続けていることを実感しています。引き続きCEOとして、日立グループ28万人に「共感」を広げていきたいと考えています。
不確実性の時代だからこそ大切にすべきこと

今、世界情勢は近年にない目まぐるしい動きを見せ、企業の事業環境にはディスラプティブな変化が起き続けています。生成AIは急速に進化し、ビジネス環境を劇的に変えました。かつて「フラット化する世界」が喧伝されていた国際関係に目を移せば、通商問題や紛争など、分断が世界各地で進行しています。こうした変化を、経営者がすべて事前に見通すことは困難と言わざるを得ません。
私は、不確実性の高い世界における経営の一つの解は、アジリティ、すなわち変化に即応する速度を高めることではないか、と考えています。予測のつかない変化は脅威ですが、それに即応できれば機会とすることもできます。早く動いた結果失敗しても、すぐ改め別の道をゆけばよいのです。
同時に、予測のつかない変化が相次ぐ中では、“ Do things right”(うまくやる)ではなく、“Do the right thing”(正しいことをやる)が大切だと考えます。日立にとっての“the right thing”とは、自らをデジタルセントリック企業へと変革して企業価値を向上し続けることであり、それを通じて「ハーモナイズドソサエティ」の実現に貢献することです。世界で分断が進行する今、調和のとれた社会の実現への貢献を目標として掲げることは、「和」を重んじる日本にルーツを持ち、グローバルでの課題解決に取り組んできた日立だからこそできる取り組みだと、使命感を感じています。
日立グループ28万人の力を団結し、ステークホルダーの皆さまからの信頼に足る実績を積み重ねながら、将来にわたって「社会に貢献する」という日立グループの存在意義を果たし続けてまいります。
執行役社長兼CEO
德永 俊昭